�Ꮌ���̍�Ə�ł́A
�܂�����Ȃ��ؐ��i�E�@�ې��i������ł������̂������ł���B
�E�H�����@�@�@�@�@�E�H���ΒT���ʐ^�W
�@�@���M�s�X�̐�����10�����A�E�H�����̕t�����Ɉʒu���A������x���Ő������鏬�͐��g��̍��ݑ�n�i�W��18���j�Ɣ×����ɂ��̍L����������Ă���A�ꕶ���������t�̈�Ղł���B

�@�@��n���̑����쑤�ɎΖʂɂ́A���w��j�Ձu�E�H���v������A���̃X�g�[���T�[�N���Ƃ͈�A�̈�Ղł���B
�@�@�Ꮌ���́A���̏��͐�̑����Z�H�ő�n�[�����ꂽ�p�����ɑ��݁A�L�x�Ȑ�����L���鍕�F���A�D�ƍ��̌ݑw��1�`1,5���̌����ő͐ς��A����u��20���_���z����╨���p�b�N���ꂽ�悤�ȏ�ԂŖ�������Ă����B
�@�@�y��E�Ί�ނ͖ܘ_�ؐ��i�E�@�ې��i�E���H�i���^��q�E���R�Ȃǂ̑�ʂ̗L�@���╨����������A�t���[�e�[�V������y�됅��ɂ����ׂȓ��A���⑶�̂Ȃǂ����o����Ă���B
�@�@�o�y�╨�ŁA�ؐ��i�ł͕��q�E�₷�E�����Ԙg�Ȃǂ̋��J��A���i�����с��j�����ޖ܂��͋����ŁA��[���������[�Ɏ���ɏ]���Ĕ���������n�`�̂��́j�E�Ε����E����E��⊄�ށE�ށE�ۖ؍ނ̊e���H�i�Ȃǂ̏�����ށA���J��E���y��E�����i�A�|�A�ށA���E�����ށE�Y�Ȃǂ̉��H���ށE�r��ށA�Y���ނȂǂ������B

�@�@���،��ނ͑�n��ɂ��������ؒ����ƍ��v������̂ŁA���̌�̏��M�s����ψ���̃X�g�[���T�[�N���j�Ր��������ɂ����Ă����ӂ��狐�،������o����A�u�E�H���v�̎�������ؒ�����芪���Ă����\��������B
�@�@���H�i�ɂ́A�َؑ������A�鎽�h�R�E�鎽���H���ʁA�����i���݂���B
���琻�i�ł́A���t�𗭂߂��e���ԍʂ����f�Ђ�����ق��A�����t���ⓕ�Ηp�Ƃ��āA�����͑@�ۍޗ��Ƃ��ėp����ꂽ���̂�����B
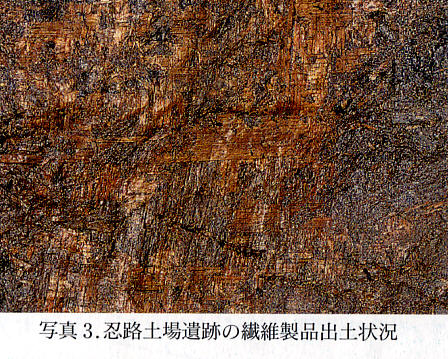
�@�@�@�ې��i�ł́A�~����E�������ɕґg���ꂽ���̂��ނƂ��̐��i�A�����A⣁i������߂��B�ׂ����|��҂�ŁA���܂��͒ꖳ�������̌`�ɑ���A�����������o���Ȃ��悤�Ɍ��ɘR�l(�낤��)��Ȃǂ̂��������������́B�����B������ȁB�����B�ǁB�j�E����̂ق��A�ʐF���ꂽ�҂ݕz�₽���g�ɕt�������Ԏc�ЁA���H�i�ŏグ���R�E���Ȃǂ�����B
�@�@�n�`��w���A�╨���z����݂�ƁA�Ꮌ�n���͐�̔×��ƈړ��̌J��Ԃ��ɂ���ēD�E�����͐ς��A�×����Ƃɋ@�ʂ��̈��肵���ʂ��`�����ꂽ�B
�@�@�×����ɐ����ʂƂ��A�ؐ��i���n�߂�Ƃ��鑽���̈╨���c���ꂽ�̂ł���B���̐����ʂ̂����A���Ɉ╨��ؑg��\�E���ނȂǂ��W������X�y�[�X����}�R�i�K�łV�����m�F����A����K�v�Ƃ����Ƃ��s���u��Ə�v�Ƃ��ĂƂ炦��ꂽ�B
�@�@��Ə�͐H���𒆐S�Ƃ��铮�A�����H�⎽�H�A�@�ې��i���̏������敛���i����ƍl������B
�@�@���؍ނ⌚�ށE�Ȃǂ̖ؐ��i�E�@�ې��i�����Z�p�̍���������A�ȈՓI�Ȑ����H�����s���Z�p���x���ɂ͏\���B���Ă������̂Ǝv����B


�@�@�P����Ə�͒����ƌ��ނ̏o�y�A10�����̏ēy�Ɩؑg�A�ؑg�̎���ɏW������ҕz�E�X�_����@�ې��i�E�N���~�E����A����Y�����̕t��������^�[���y���R�d�`�E��Ȃǂ̓���ނ̏o�y����A��Ƒ�ł���ؑg�𒆐S�ɏ�����F���������킹���A�����H�i���H��Ɛ���ł���B
�@�@�S����Ə�́A���ށE�M�`�Ќ��e��E��Ȃǂ̖ؐ��i�A�e��̓y��A��E�����E�~����Ȃǂ̑@�ې��i�A�N���E�N���~�̏W������A��͂�A�����H�i���H�̏�Ɛ��肳���ƂƂ��ɁA�����h���Q�_�E�ԐF�痿��t���ꍭ�̎c��y��̏o�y�́A���H��Ƃ̓W�J�ƌ��Ď���B
�@�@�U����Ə�͍��܂蕔���Ɍ��ނ₷�����@�ې��i���o�y���A�����ɏ����������Ă������Ƃ�����B
�@�@�ؑg�݂̎��ӂɂ͑@�ې��i�E���炪�����A�[���y���r�t�M�E��E��^�����Ȃǂ̖ؐ��i�A���A���������p����Y�����A�b���Ђ̏W���ȂǁA�����I�ȐA�����H�̏��������\�E�╨���o�y���Ă���B
�@�@���̂悤�ɖؐ��i�E�@�ې��i�E���H�i�͒P�Ƃŏo�y������̂ł͂Ȃ��A�P�ƂŎg����̂ł��Ȃ����Ƃ��������B
�@�@�ؐ��i�E�@�ې��i�E���H�i�Ƒ��̓���i�y��E�Ί�E���i��Ȃǁj�Ƃ̑g�ݍ��킹�ŁA�ꕶ�E���ꕶ�l�̓��퐶���̉c�݂�_�������������Ă������̂ŁA�u�v�������Ă����ꕶ�`���ꕶ�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B
�@�@���Ȃ��Ƃ��Ꮌ���̍�Ə�ł́A�܂�����Ȃ��ؐ��i�E�@�ې��i������ł������̂������ł���B
�i�k�C�������������Z���^�[�@�O�Y���l�j