
海人が日本へ!
そしてアメリカへ!
(「海を渡ったモンゴロイド」太平洋と日本への道 後藤 明)
遠くオセアニアで後にポルネシア人を生み出した海人文化が、日本列島に既に及んでいた可能性がある。
縄文時代の日本にオーストロネシア系文化が及んでいたとする研究者は救い無くない。
例えば神話学者の吉田敦彦は、神話論的な立場から縄文土偶の謎に迫っている。
アジアに進出した新人類は、移動する民であった。
彼らは、数万年前、オーストラリアやニューギニアへと渡海した。
日本列島では、確実なところでは今から三万年程前、旧石器時代の遺跡が存在する。
日本列島では大陸に近いので最も古い遺跡があると思うのであるが、それは今後の調査に期待する。
南方に限れば、鹿児島県の種子島や徳之島では旧石器時代の遺物が発見されている。
旧石器時代に人類が島伝いか、或いは氷河期に陸橋になった琉球列島やトゥンハイランドを移動してきた証拠であろう
徳之島の遺跡は二万〜三万年前の物である。
琉球列島においては、それ以外の旧石器時代の証拠は人骨である。
日本の確実な最古の人骨とされる港川人。
これは沖縄本島で発見された化石人骨。その年代は二万年前である。
この人骨の特徴は、スンダランドの古モンゴロイドの形質を受け継ぎ、彼らと沖縄人の橋渡しになると考えられている。
最終氷河期が終わり、日本が完全に島になったのが、今から一万二千年程前のことである。
その時花咲いたのが縄文文化である。
日本列島の地理的特徴を考えると、縄文文化には北から或いは朝鮮半島から、色々な影響が及んだと思われる。
更に海を越えて、南方から文化が及んでいた証拠がある。
例えば鹿児島県の栫ノ原遺跡(夏を過ごした「栫ノ原遺跡」
http://sennboku.web.fc2.com/bunarintokodaisi/minamikiyuusiyu/A/kakouinohara.html
や上野原遺跡(国内最古級の定住生活
http://sennboku.web.fc2.com/bunarintokodaisi/minamikiyuusiyu/uenohara/uenohara-html.html がある。
今から一万一千年から九五百年前の縄文時代の遺跡である。
これらの遺跡からは、オーストロネシア(かつてマレー・ポリネシア語族と称された語族で、700以上という言語の数でも、西はマダガスカル島から東はイースター島、ハワイにおよぶ地理的広がりからみても、世界最大の語族のひとつである。)世界に広く分布する丸呑み形石斧や石蒸し料理の跡が発見されている。
丸呑み型石斧は、手斧としてカヌーのように木を掘り抜く道具を考えられている。
世界最古の丸木舟工具
http://www14.plala.or.jp/bunarinn/dairyA/encarta/kurosio/marunomi/marunomi.html
また石蒸し料理とは主にオセアニアの民族が行っていた調理法だ。穴を掘って焼けた石を入れ、その中に葉でくるんだ肉やイモを並べて蒸し焼きにする方法である。
更に、上野原遺跡からは大きな壺型土器が出土している。
主に弥生時代に出土し用途的には穀物の貯蔵用と考えられている土器形式である。
遺跡では土中のプラントオパール(植物硅酸体)の分析により、アワ、ヒエ、ジュズダマのような雑穀類が利用されていたのではないか、と推測されている。
これらの雑穀には、台湾周辺のオーストロネシア民族が持っていたとされる種類が含まれている。
遠くオセアニアで後にポルネシア人を生み出した海人文化が、日本列島に既に及んでいた可能性がある。
縄文時代の日本にオーストロネシア系文化が及んでいたとする研究者は救い無くない。
例えば神話学者の吉田敦彦は、神話論的な立場から縄文土偶の謎に迫っている。
長野県の釈迦堂遺跡で出た土偶が、意図的に壊されるために作ってあったことに注目している。
これは「古事記」のオオゲツヒメ神話のように、神は死ぬことによってその体から作物を生じたとする信仰に基づく儀礼であると考えられている。
即ち「死体化世生型神話」であり、東南アジアやオセアニア、更にアメリカ大陸などにも色濃く分布する形式の神話である。
吉田はこの神話が、縄文時代に、オーストロネシア系ないし先オーストロネシア系文化とともにもたらされた文化要素である、と考えている。
「海上の途」柳田 国男
この著作は日本人の起源に関するものである。
日本人の祖先は、稲を携えて、琉球列島を伝って日本列島に到来したと考えたのである。
稲作は揚子江流域に起源を持つが、中国南部から直接に北九州へ、或いは朝鮮半島を経由して北九州へ伝播した、というのが現在の定説である。従って、琉球列島沿いに今我々が食べている米(ジャポノカ型)が入って来田、という柳田の仮説は受け入れられていない。
しかし、その後、幾人かの研究者が柳田の「海上の道」論のアイデァを発展させてきている。
例えば、熱帯性のジャポニカ型の米、或いは米以外の文物がこのルートで日本列島に入ってきたことは十分あり得る。
柳田がジュジュダマに注目していたことも確かである。
柳田は、中国南部から貝貨用の宝貝を求めて來た人々が琉球列島沿いに稲作を伝えたとする仮説を示している。
柳田が「人間がなぜ海を越えるのか?」という問いの主体として、魚をとり貝を愛でる漁撈民でと同時に、畑を耕す農耕民でもある人々を想定したところにあると思われる。
それを理解するなら、仮に稲やイモといった作物をもたらした人々だからといって、我々の描くイメージの「農民」を考えてはならない。柳田は人間の本質を鋭くみているのであって、これが私の「海上の道」論の評価である。
弥生時代初期の遺跡は海岸部や低地に多く、又稲も低地を中心に栽培されたらしい。
そして、西日本特有の遠賀川式土器が、青森・秋田・山形の各県でも発見されている。
この土器は東北地方の太平洋側でも発見されているが、その移動してきたルートは日本海側であると考えられよう。
稲作は北九州から近畿地方へ瀬戸内海を通って伝えられ、次いで日本海沿岸に伝わったのだろう。
中村慎一によれば、本州最北端への稲作の急速な伝播スピードは、騎馬民族を除くと、オーストロネシアの太平洋への拡散以外に匹敵するという。
つなり、初期の稲作の伝わったメイン・ルートは「海の道」であったのではないか。
又、弥生時代には、日本海沿岸に「タマの道」があったことが知られている。糸魚川の翡翠や佐渡島の碧玉製の球が、日本海側を通って、九州や北海道に運ばれている。
このような事実は、常識的に「農民」「漁民」と分けるような枠組みでは捉えきれない人々の存在を意味している。
日本に稲作をもたらしたのも、南太平洋に根菜農耕をもたらしたのも、農民でも漁民でもない、「海人」ではなかったかと考える。
柳田国男の「海上の道」論の真の価値は、そのような海人に関するモデルを提供したことになる。
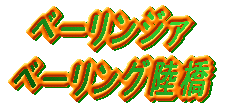
http://kodaisi.gozaru.jp/kitanokodaisiB/kazan/berinjia/berinjia.html
先住民の起源・アメリカ大陸へ
人類のアメリカ大陸への移動は、北から、即ちシベリアからアラスカを経由した、というのが定説となっている。
つまり、サフル大陸の居住と同じで、氷河期に海水面が低下し、シベリアとアメリカの間にあるベーリング海が干し上がった時期に行われたものと思われる。
そのときは、ベーリンジアという低地ができ、両大陸がつながっていた。
その年代は氷河期の最盛期の五万年前、次は二万年前の時期である。
アメリカの先住民は、このような時期にシベリア或いは北東アジアから移住した人々の子孫である。
この地に古くからヨーロッパ系住民、或いはアフリカ系住民との混血が行われており、状況は簡単ではない。
系統が一つに絞れないと言うことになる。
(「海を渡ったモンゴロイド」太平洋と日本への道 後藤 明)